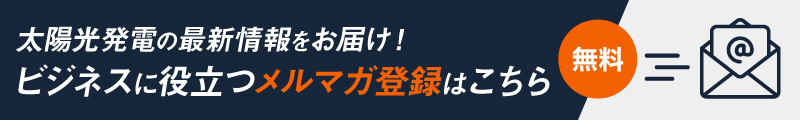再エネの国際テーマはベネフィット。京大安田教授の視点
2018/03/26
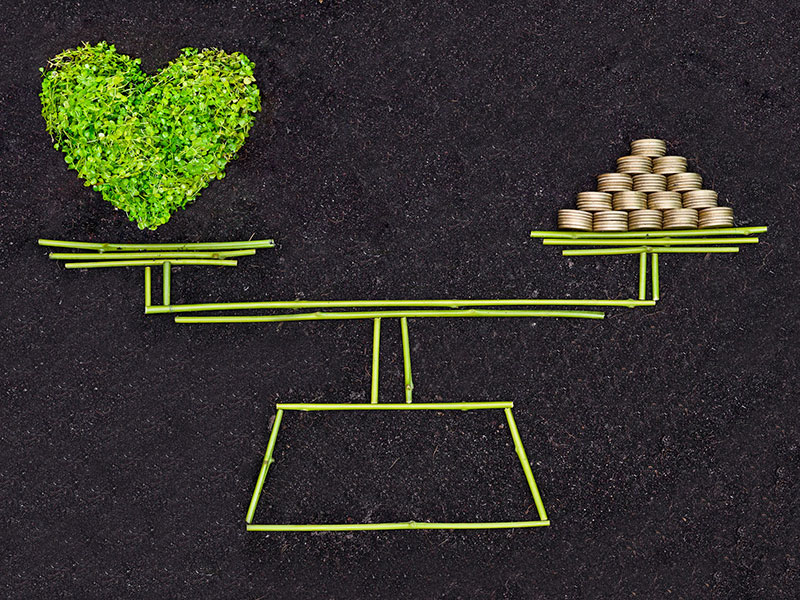
再エネを考える際に議論となるコスト。しかし、そればかりに目を向けていて、建設的な議論ができるのだろうか? 送電線の空き容量問題に鋭く迫り話題となった安田京大特任教授は、再エネのベネフィットを考えることが疎かにされていると指摘する。
再エネの社会的便益は
投資額の4〜15倍
日本では、再生可能エネルギーの議論において、ベネフィット(社会的便益・価値・バリュー)について語られることがほとんどありませんでした。再エネの導入拡大を考えるにあたっても、コストばかりに関心が集まり、ベネフィットの検討が疎かにされているように感じられます。
しかし、IEA(国際エネルギー機関)やIRENA(国際再生可能エネルギー機関)など、国際的な合意形成を図る機関では、ベネフィットこそが大きなテーマとなっています。再エネのベネフィットを定量的に計算する作業も進められています。
再エネには様々なベネフィットがありますが、例えは次のものが挙げられます。
①化石燃料の削減による健康被害の抑制、輸入依存度の低減、自然保護。
②CO2削減による異常気象の抑制、生態系への影響。
③その他、雇用創出効果など。
これらは特定の企業や産業界だけが得るプロフィット(利益)とは違い、国民全体あるいは地球市民全体が恩恵に浴するものです。この価値を定量化し、金額に置き換え、正当に評価していこうというのが世界の潮流なのです。
例えば、IRENAは、気候変動(地球温暖化)を防ぐためには世界で年間約3000億ドルの再エネ投資が必要だとする一方、これを怠ると年間1.2〜4.2兆ドルの損害が発生してしまうと試算しています。再エネにコストはかかるが、実はコストの4倍から15倍のベネフィットを生んでいるというわけです。
再エネのコストを考えるときには、このベネフィットを併せて考えなければなりません。ベネフィットを定量化し、その意義をきちんと評価しなければ、公正な判断はできないはずなのです。
再エネのベネフィットは、損害を未然に防ぎ、マイナスをゼロに戻すという性格のものですから、効果は実感しづらいかもしれません。しかし、これを軽視して、コストばかりに目を向けていては、将来にツケを回すことにもなりかねないのです。
プロフィール
京都大学大学院 経済学研究科再生可能エネルギー経済学講座 特任教授
安田 陽
1994年、横浜国立大学大学院博士課程修了。工学博士。関西大学システム理工学部准教授を経て、2016年9月より現職。現在の専門分野は風力発電の耐雷設計および系統連系問題。
取材・文/廣町公則
『SOLAR JOURNAL』 vol.24より転載


 マガジン
マガジン セミナー・勉強会
セミナー・勉強会 オンライン展示会
オンライン展示会