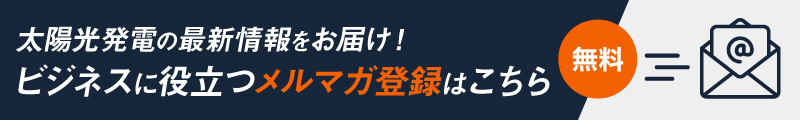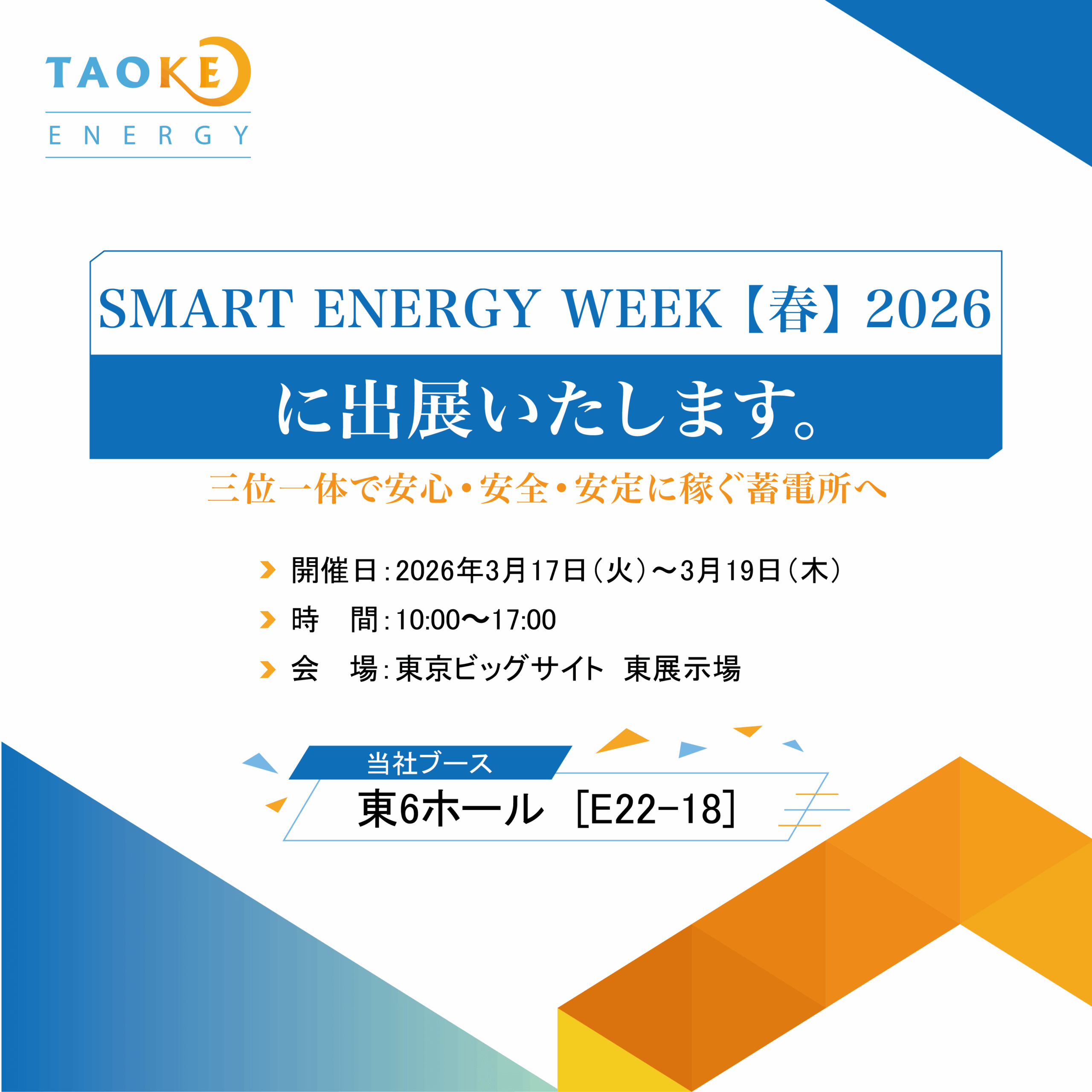“地域密着型”新電力の強さとは? 福岡県「やめエネルギー」の事例
2019/02/04

福島電力の経営破綻など、新電力の“淘汰”が進む中、成功を収めている企業も確実に存在する。新電力のコンサルティングも手がけるエネルギージャーナリストの北村和也氏が、地域電力の本質を解くコラム第2回(前編)。
選別の時代を生き残る
「地域密着型」の新電力
前回のこのコラムで、新電力が選別の時代を迎えていることを書いた。
福島電力の問題や大きな赤字を出した大手の新電力などを取り上げて、今後の小売電気事業者の行く末を考えたものであった。そこでは、あえて「選別」という言葉を使ったが、選別というからには、捨てられる側ばかりではなくピックアップされる側が無くては選びようがない。
そこで、新しい年を迎えて、地元に根付いて活動する「地域密着型の新電力」をいくつか紹介していきたいと思う。これこそが選別の時代を生き残るひとつの在り方だと考えるからである。
いずれもまだ全国で取り上げられることがほとんどない無名の新電力であるが、一定の実績と可能性が秘められている。ある程度の具体的な内容を示す必要があることから、いずれも筆者が深く関わっている新電力であることを前もって断っておく。
地元73社の
民間資本の結集
まず、福岡県八女市で立ち上げられた、やめエネルギー株式会社をご紹介する。
やめエネルギーの第一の特徴は、完全な地元の民間100%の資本で成り立っていることである。お隣のみやま市にあるみやまスマートエネルギーが55%市の資本が入った第三セクター形式で、日本のシュタットヴェルケを目指しているのに対して、こちらは純粋な民間会社である。自治体が入るか公共施設への供給がないと事業性が担保できないという“常識”から外れた新電力から紹介していくことにする。
このやめエネルギーの中心会社は太陽光発電施設の施工会社であるが、それをサポートするように地域の70を超える会社が資本を出している。地元会社が多数参加するのは悪いことではない。他の地域でその話をすると「おお、すごい」というポジティブな反応が返ってくることが少なくない。それは確かに理想的に聞こえるかもしれない。また、資本参加した会社は一番目に電気の顧客になってくれる可能性が高い。正直言って、資本の参加を増やす狙いの一つはそこにあった。
しかし、それが100%プラスに働くかというとそう簡単ではない。数が多ければモチベーションも多様で、何より責任が分散されがちである。物事が決まらないという決定的なデメリットが発生するリスクは高い。
やめエネルギーでは、中心となる会社とサポーター的な多くの地元企業というように、役割を分けている。前述の地元の太陽光発電の施工会社が核となり、実際の小売電気事業を回しているため、これまでのところ運営面での問題はない。


 マガジン
マガジン セミナー・勉強会
セミナー・勉強会 オンライン展示会
オンライン展示会