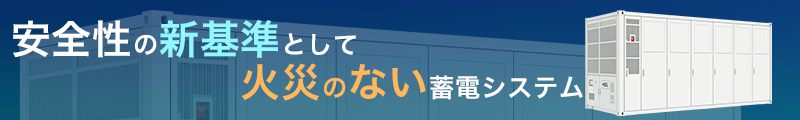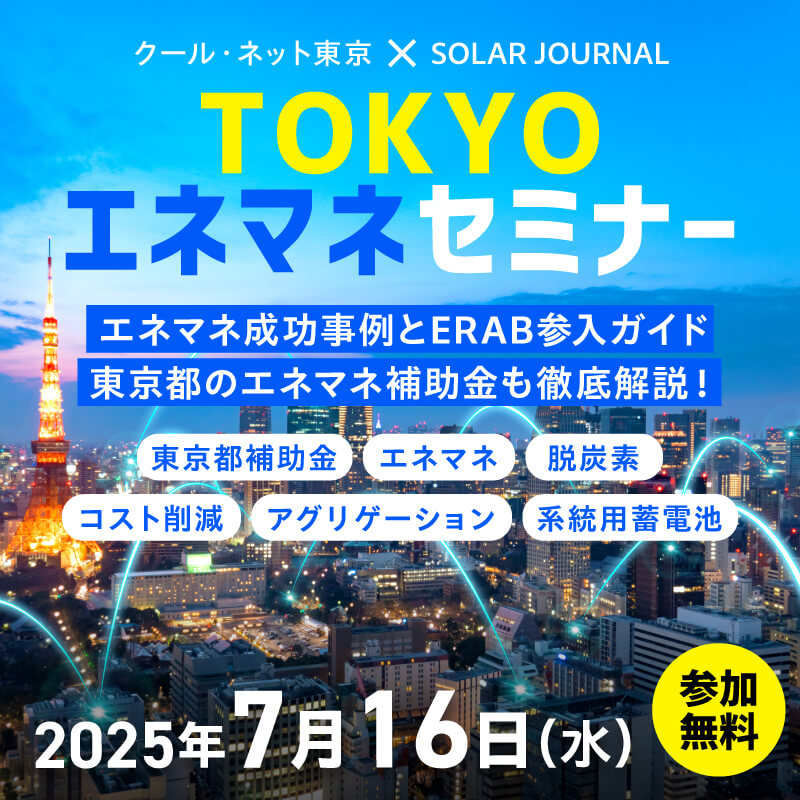カーボンニュートラル宣言から10ヶ月「なぜ脱炭素が必要なのか」原点に戻って考える
2021/08/23

地球温暖化の影響による自然災害が国内外で頻発している。そんな今こそ、脱炭素の推進、再エネの拡大の理由について再認識することが必要なのではないか。エネルギージャーナリスト・北村和也氏による連載コラム第28回。
8月も半ばなのに、連日雨が続いている。今日(8月16日)は東京近辺の気温は20度を少し超えるほどで、肌寒い。ふと、数年前の真夏にドイツに行った時のことを思い出した。その時も似たように、しとしとと連日雨が降り、驚くことに気温は10度を少し超えた程度にまで下がった。太陽があまり出ないのがドイツの天気の特徴といっても8月でこれはおかしいと首を傾げた。
そのドイツの今年の天候はさらに異常である。冬は非常に暖かく、春は一転低温だった。そして、7月に大量の雨が降って大洪水を起こした。100人を大きく超える犠牲者が出るなど、これまではありえないことだった。地肌をざっくり切り裂いて大きくこそげ取ったような光景に愕然とした。
ドイツのシュルツェ環境相は、「気候変動が到来した」と語り、メルケル首相が「気候変動に断固として取り組む必要がある」と強調した。
数十年に一度が毎年に
私の住むのは、ほとんど水が出るようなことのない恵まれた場所だが、線状降水帯が繰り返し押し寄せる九州から中国、中部地方にかけて、すでにがけ崩れなどで犠牲者が出ている。九州北部や広島などつい2、3年前多くの人命が奪われた場所でまた災害が起きている。
気象庁の特別警報は、「数十年に一度の、これまでに経験したことのないような、重大な危険」という定義である。ところが、起きているのはこのところ、ほぼ毎年と言ってよい。異常な状況が常態化したのは、地球温暖化の影響であると考えざるを得ない。
そんな中の8月初旬、IPCC:気候変動に関する政府間パネルが、第6次評価報告書の一部として、地球温暖化の科学的な根拠を示す内容を発表した。そこでは、温暖化が人間の影響であることに「疑う余地がない」と、断言している。一部でCO2増加と温暖化の結びつきを否定する向きもあるが、それを切って捨てた。また、世界の平均気温が、産業革命前に比べてすでに1.1度上がり、2040年までに1.5度に達するという見通しを明らかにした。2050年を目標に脱炭素を完成させることさえ多くの困難がある中、意気をくじきかねない情報である。
一方で、二酸化炭素の排出を着実に減らせれば、いったん1.5度を超過しても今世紀末に向け、再び下がるとの情報も付け加えられている。あきらめれば終わりで、今、行動すれば、まだ間に合うと考えるしかない。
災害の激増が温暖化の行く末
現状の気温上昇は1度程度であるが、それでも災害が10年に一度起きる確率は、熱波で2.8倍、豪雨で1.3倍になってしまった。これが2度だと熱波で5.6倍、豪雨で1.7倍になるという。4度上がると、熱波9.4倍、豪雨2.7倍となる。猛暑に続く大雨と被害に当てれば、恐ろしさがよくわかる。
日本は世界でも異常気象の発生率が高くなった国と統計にある。温暖化の影響を早めに受け始めたのである。前述した数十年に一度の特別警報が、年中行事化していることが証明している。
私たちはなぜ脱炭素に注力しなければならないか。今回のコラムのテーマは、ここに行きつく。IPCCが温暖化の原因を二酸化炭素の上昇と断言し、私たちがこれからどんな行動をとらなければならないかははっきりしている。これは、政府も、企業も、地域も個人も同じ課題である。
もう一度、
脱炭素の目的を考える
昨年10月末の日本政府のカーボンニュートラル宣言から10ヶ月が経とうとしている。この間、矢継ぎ早に新しい脱炭素の施策が出された。日本政府には珍しいスピードで、企業や自治体の反応も強い。主要企業(日経平均の225社)の4割が二酸化炭素の実質ゼロ宣言をしているという。4か月前の調査なのでさらに拡大しているのは確実である。環境省の進めるゼロカーボンシティ(2050年二酸化炭素実質ゼロ宣言)の表明は、7月末現在で432自治体におよび、そこで暮らす人口は1億1000万人を超えた。もはや、宣言しない方が少数派である。
筆者の仕事は、民間企業や地域での再エネ拡大や最近は脱炭素のアドバイスなので、直接関連している。おかげで忙しさは増している。ところが私も含め、どうやって再エネ電力を手に入れるかなど、脱炭素の実現方法に走ってばかりいるかもしれない。つまり、テクニカル=技術的なツールを求めて動き回ることにかまけがちである。
今、起きている悲惨な災害やそこで被害を受ける人々の大変さに接しても、温暖化とのつながりを心に刻み切れていない。ここでもう一度、少し立ち止まって「なぜ」を考えたい。脱炭素の推進、再エネの拡大の理由である。持続的で将来にわたって、この地球上で生命がながらえることができるように今を改善すること、私たちの「なぜ」の答えは、それを外しては存在しないはずである。
堂々と脱炭素へ
個別の理由の中には、CO2を減らす取り組みをすることによって企業の存続を図ることや、もちろん、脱炭素のトレンドでビジネスチャンスを手に入れることもありうる。それは悪いことでは決してないし、重要な要素である。私も企業などに対してそうアドバイスをしている。
しかし、根源にあるのは、人類が起こした気候変動という未曽有の困難をどう乗り越えるかである。それを見ないと、危機感が持てなかったり、テクニカルなことばかりに拘泥したりする。現実的でないとか、理想主義だとかの批判はそこに起因することが多い。スウェーデンの環境活動家、グレタ・トゥンベリさんに対する言われなき、かつ卑しめるような言葉の背景にはそんな共通点があるかもしれない。
今起きている災害を少しでも食い止め、人が安心して住める場所を確保するため、脱炭素への努力は、堂々と行うのが良い。
プロフィール
エネルギージャーナリスト。日本再生可能エネルギー総合研究所(JRRI)代表。
北村和也
エネルギーの存在意義/平等性/平和性という3つのエネルギー理念に基づき、再エネ技術、制度やデータなど最新情報の収集や評価などを行う。
日本再生可能エネルギー総合研究所公式ホームページ

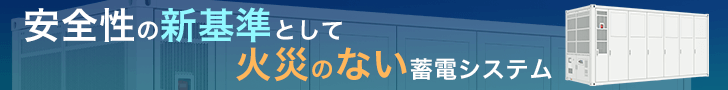
 マガジン
マガジン セミナー・勉強会
セミナー・勉強会 オンライン展示会
オンライン展示会