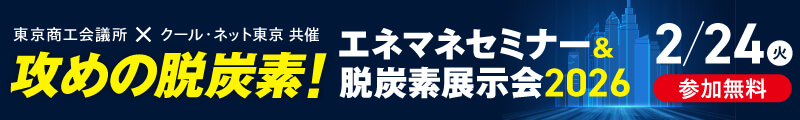【飯田哲也さんコラム】営農型太陽光発電の現状と課題。ルールをゼロから見直して「農家FIT」の導入を
2025/09/30

エネルギー安全保障と農業再生の鍵を握る営農型太陽光発電。ドイツの先進事例に学び、農家主導の発電に対しては農地転用規制の撤廃や「農家FIT」の導入など、合理的かつ持続可能な政策への転換が、日本においても急務となっていると、環境エネルギー政策研究所 所長の飯田哲也氏が語る。
エネルギーと食を支える
営農型太陽光発電の苦境
「令和の米騒動」の根本には、国民生活と安全保障で最も重要な農業に関して、大局観に欠けた場当たり的な農政がもたらした構造的な問題があります。エネルギーは気候危機の原因となっているだけでなく、化石燃料を年間20数兆円(GDPの約5%)も輸入し、国内自給率は15.2%(2023年度速報値)とOECD諸国の中でも極めて低く、安全保障的にも脆弱な水準です。この状況は農産物でも同様で、食料自給率はカロリーベースで38%(23年度)と、日本は年間10数兆円を食料の輸入につぎこんでいます。
そのエネルギーと農業が交わるところにあるのが「営農型太陽光発電」(営農ソーラー)です。太陽光発電政策の観点から見ると、12年に始まった固定価格買取(FIT)制度は、設備認定時の買取単価を維持する制度設計の失敗をはじめとする将来見通しの甘さによって、開発に伴う環境破壊などを引き起こしてしまいました。また、営農型太陽光発電をめぐっては、農林水産省の13年の通知を根拠とする、支柱に農地転用許可を必要とする「暫定的なルール」が引き継がれています。残念なことに、発電事業を主体として営農をおろそかにするケースも出現したことなどから、本来、エネルギーと農業の救世主であるべき営農ソーラーは、逆に批判的な目で見られています。
現実や技術革新を考慮した
ルールの見直しが必要
海外に目を向けると、ドイツでは、太陽光発電のポテンシャルがある農地をゾーニングして、生産性が低い農地を中心に営農ソーラーを積極的に導入する施策を推進しています。これに加えて、マンションのベランダなどに手軽に設置するプラグインソーラーの導入などで太陽光発電の導入が急増し、30年に発電電力量に占める再生可能エネルギー電源を80%に高めるという目標を前倒しで達成できる見通しです。
日本にも、建築物や農地、駐車場などのデッドスペースに、太陽光発電の導入のポテンシャルがあります。中でも、農地のポテンシャルは高く期待されています。日本は営農ソーラーのパイオニアであり、これまでにも多くのソーラーパネルが農地に設置されてきました。しかし、1つひとつの案件の規模が小さいため、合計で約1GW程度(飯田氏推計)の導入量にとどまっています。
営農ソーラーの導入を加速するため、13年の暫定ルールをゼロから見直すべき時だと考えています。まず営農ソーラーを、農家が行うものと発電目的の第三者のものとに区別して、前者は支柱の農地転用を求めるルールは撤廃すべきです。以前は、コンクリート製の温室も農地転用の手続きが必要でしたが、現在は不要になっています。農家が行う営農ソーラーは、資金調達と投資回収が容易となるよう、ドイツと同様に有利な価格でのFIT、いわゆる「農家FIT」を導入することで経営基盤の改善に生かします。営農型太陽光発電の下で栽培する農作物の収量を一律8割以上とする収量基準の見直しも必要でしょう。農作物の収量は、農作物の種類や気象条件などさまざまな要因に左右されるものです。収量の目標は、過去の統計を生かして科学的に定めた参考値をガイドラインで示す程度でよいかと考えます。
近年は営農ソーラー設備の技術革新が進んでおり、細型パネルや可動式・垂直式などの先進的な技術が登場しています。こうした変化を踏まえて、農業にもエネルギーにも望ましいさまざまな営農ソーラーに挑戦するべきでしょう。
農業のデジタル化で
生産性や収益性を向上すべき
こうしたルールの見直しは、データに基づいて科学的に行わなければなりません。現在、営農ソーラーの申請手続きは文書によるものが多く、データ化されていません。すべての申請業務をデジタル化し、必要なときにアクセスしやすくすることで、行政手続きの効率化やビッグデータの分析、ノウハウの横展開が可能になります。農業分野のデジタル・トランスフォーメーション(DX)を進めてアップデートすることで、生産性の向上や、営農ソーラーなどの活用による収入アップにもつながると確信しています。
PROFILE
NPO法人 環境エネルギー政策研究所(ISEP)
所長
飯田哲也氏

自然エネルギー政策の革新と実践における国際的な第一人者。持続可能なエネルギー政策の実現を目的とする、政府や産業界から独立した非営利団体である環境エネルギー政策研究所所長。
X:@iidatetsunari
取材・文:山下幸恵(office SOTO)
SOLAR JOURNAL vol.54(2025年夏号)より転載


 マガジン
マガジン セミナー・勉強会
セミナー・勉強会 オンライン展示会
オンライン展示会