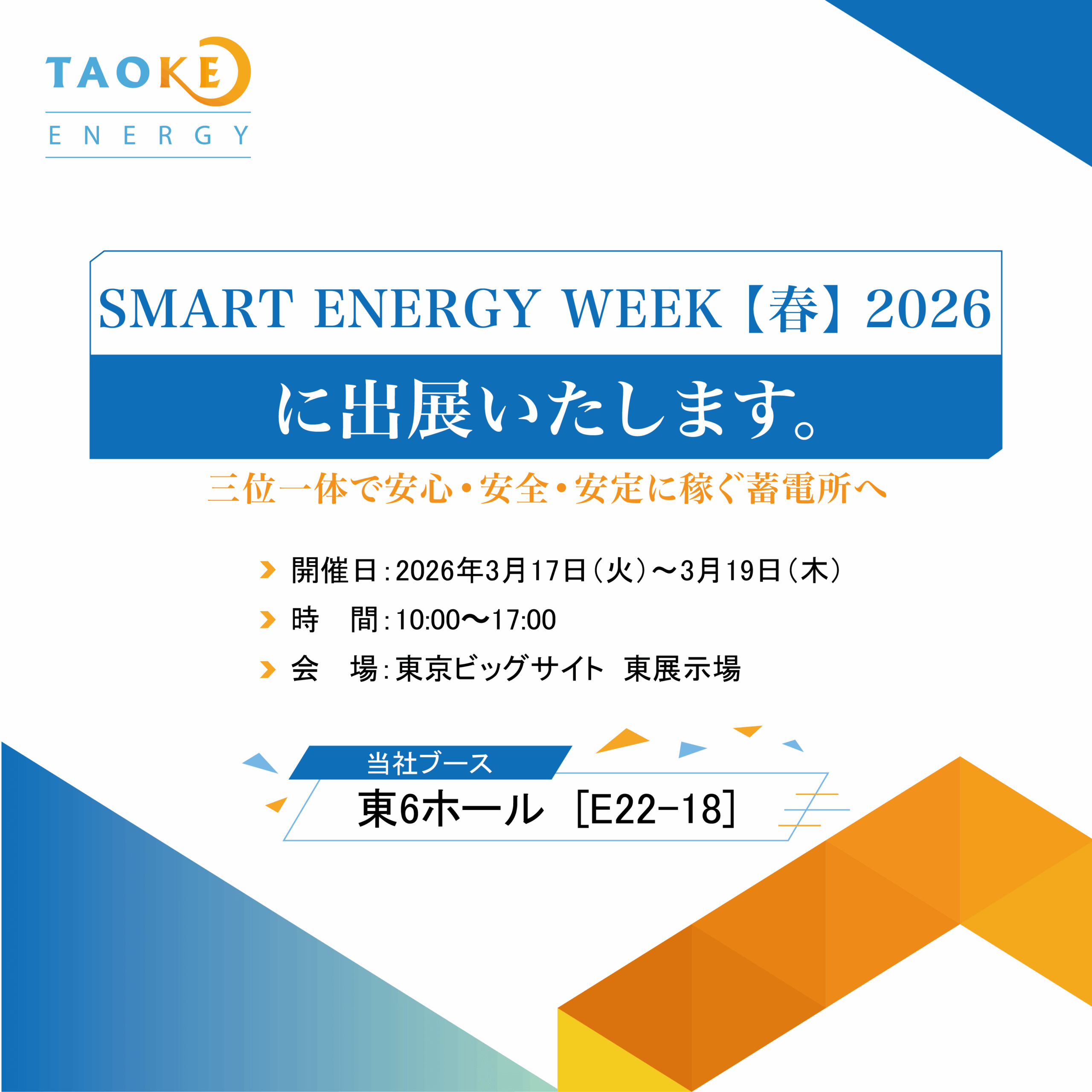【PVビジネスセミナーレポート】第7次エネルギー基本計画の論点は?
2025/05/09

2024年最後となる第31回PVビジネスセミナーは10月25日に開催(リアル会場は恵比寿駅近く)。テーマである第7次エネルギー基本計画にふさわしいスピーカーが多数登壇し、会場を訪れた聴衆とオンラインでの参加者はじっくりと耳を傾けた。さまざまな学びを得られる場になっていたようだ。セミナー後の懇親会も盛況。太陽光業界で働く者同士がビジネスの情報交換などをしつつ、楽しい時間を過ごした。
1. 青森県民生協の脱炭素実践~オンサイトPPAとオフサイトPPA~
2. 第7次エネルギー基本計画と中小企業の脱炭素化
3. GoodWeの日本市場向けエネルギーソリューション事例のご報告
4. FIT発電所とFIP発電所、計画どおりに進まないのはどちらか
5. ソーラーエッジのリパワリング
6. JET認証取得!~日本市場に変革をもたらすSG5.5RS-JP~
7. 横浜市 脱炭素に対応したまちづくりへの挑戦
8. Re-Powering? FIP転? 蓄電池併設?
青森県民生協の脱炭素実践
~オンサイトPPAとオフサイトPPA~
再エネ100宣言 RE Action 参加団体
青森県民生活協同組合 電力販売課
北川 純一氏

青森県民エナジー株式会社
取締役
富岡 哲平氏

青森県の再生可能エネルギーのポテンシャルは、県内で使用するエネルギーの約20倍。電気の地産地消を推進して県外へのお金の流出を止める。課題は再エネ導入のコスト。
第7次エネルギー基本計画と
中小企業の脱炭素化
総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 委員
再エネ100宣言 RE Action 代表理事
東京大学未来ビジョン研究センター 教授
高村ゆかり氏

現状のエネルギーシステムからの転換、エネルギーの脱炭素化、とりわけ電力の脱炭素化が急務というのが共通認識。中長期的な視点を持ち、目指すシステム転換を追求すべき。
GoodWeの日本市場向け
エネルギーソリューション事例のご報告
GoodWe Japan株式会社
執行役員社長
伊里奇氏

BIPVソリユ̶シヨン(軽量屋根用に設計)を紹介。1.6mm強化ガラスを使用して十分な強度を獲得し、クランプと熱溶着で設置できる。TUV認証済み、かつJPEA登録済みである。
FIT発電所とFIP発電所、
計画どおりに進まないのはどちらか
華為技術日本株式会社
デジタルパワー事業部 シニアプロダクトマネージャー
前田 敏徳氏
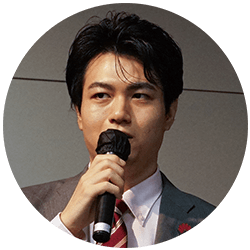
蓄電池システムを自社で構築するだけでなく、自社製のPCSと自端制御機器を使用。太陽光・風力等の発電設備に蓄電システムを併設して電力を貯蔵して夜間やスポットで放電。
ソーラーエッジのリパワリング
ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社
カントリーリーダー
谷崎 真一郎氏
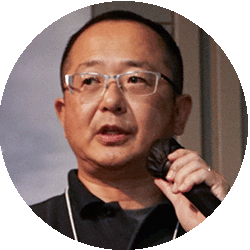
当社の強みは、他のモジュールの影響を受けずパワーオプティマイザごとに最大限の発電を可能にできること。現場で行うIV測定やIR撮影に近い情報を遠隔で取得して遠隔管理。
JET認証取得!
~日本市場に変革をもたらすSG5.5RS-JP~
SungrowJapan株式会社
技術部・技術サポートエンジニア
上田 顕広氏

5.5kWのパワコンはJET認証を取得し、9台の並列接続も可能。交流集電箱と組み合わせせて「発電量をより多く、より安全に、そして操作やメンテナンスをより便利に」を実現。
横浜市 脱炭素に対応した
まちづくりへの挑戦
横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局
カーボンニュートラル事業推進課 課長
松下 功氏

2022年度の温室効果ガス排出量は2013年比で24%の削減に成功した。令和6年度の脱炭素予算を前年の45.5億円から80.8億円に拡充し、同比で50%削減を目指している。
Re-Powering? FIP転? 蓄電池併設?
イマドキに最適な高性能N型ABCモジュール
Aiko Energy Japan株式会社
営業マネージャー
劉 澤霖氏

目指しているのはお客様の利益が最もプラスになる製品を開発、提供すること。ABCモジュールは他社のTOPCon片面製品より変換効率が約0.5%高く、出力が10W以上も高い。
Supported by
ファーウェイ

GoodWe

ソーラーエッジ

サングロウ

Aiko

SOLAR JOURNAL vol.52(2025年冬号)より転載


 マガジン
マガジン セミナー・勉強会
セミナー・勉強会 オンライン展示会
オンライン展示会