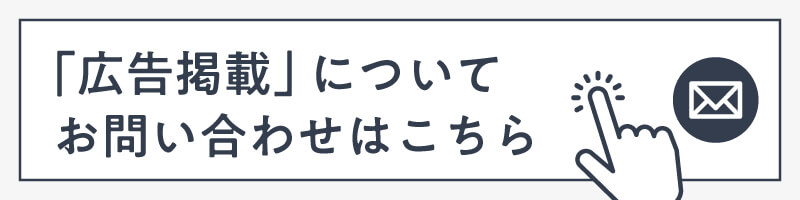脱炭素社会の実現へ、2022年は波乱と格差の年になる?
2022/01/14

国のカーボンニュートラル宣言から一年あまりが経った。「脱炭素」は誰にとっても達成しなければならない目標だが、その前にはエネルギー費の高騰や地域格差など、解決しなければならない課題が多くある。脱炭素サバイバル時代をどう生き抜くか考える、エネルギージャーナリスト・北村和也氏による連載コラム第32回。
おととしの10月末に発せられた日本のカーボンニュートラル宣言からわずか1年あまり、脱炭素を巡る動きは激しさを増すばかりである。2050年を期限に温室効果ガス排出を実質ゼロにするという目標に変わりはないが、達成の困難さに加え、その過程における課題が次々と明らかになってきている。
今回のコラムでは2022年の初頭にあたり、表出するいくつかの現象をピックアップして必要な対応などについて書いてみたい。グローバルで見ると、再エネ拡大への調整局面で現れる化石燃料不足とエネルギー費の高騰、また、企業や地域レベルで起きる格差を中心にお話しする。このコラムでも繰り返しているが、「脱炭素」はすべての団体やグループ、個人に対して関わりが求められる。他人事ではない、誰にとっても重要なテーマであることを忘れてはならない。
頻発する可能性が高い
エネルギー費の高騰
天然ガス価格の上昇が止まらない。いったん下向きになったグラフが昨年末にかけて急上昇を始めた。急変の大きな要素は、ロシアのウクライナ侵攻の可能性を背景にしたドイツへの天然ガスパイプラインの稼働を巡る危機である。しかし、その裏にあるのは、アフターコロナの経済活動の活発化や、弱い風が招く欧州の風力発電低下などである。さらに原因を探ると、化石燃料による発電施設への投資意欲の減退に行き着く。
脱炭素の主役である再エネ発電への転換が既定路線となる中、化石燃料による発電施設を造ろうという動きが急激に弱まっている。そこに、電力の急激な需要増などが起きると、昨秋から年末にかけてのエネルギー高騰が容易に発生することになる。よって、一時的な出来事の可能性がある再エネ発電の低下やエネルギー需要増、交際情勢の変化などの事象が収まったように見えたとしても、当面は高騰の根は残り続ける。
誰が考えてもわかるように、温室効果ガスを排出しているからといって、すべての化石燃料による発電を止めてしまえば、現状の再エネ発電だけでは電力需要をカバーできず、停電の危機が確実に訪れる。省エネやエネルギーの効率化は前提としてあるが、従来型の発電施設の削減は再エネ発電の増加とバランスを取る必要がある。そうはいっても、設備利用率が落ちることが確実な旧態の発電システムを誰が保持したり、新設したりするのかが、大きな問題として残る。
調整は長い目で見ればマーケットを通じて行われるだろうが、短期中期的には難しく、今起きていることは、まさに短い調整局面でのアンバランスだと考えるのが妥当だろう。
短期のリスクヘッジと
最終的な解決策
しばらくはエネルギー費が大きく変動するのを避けられないとなると、まずはそれぞれの立場でリスクヘッジを図るしかない。
発電事業者や電力小売りでは、ロングタームの契約や複数の調達ラインなどが挙げられる。一方、調整過程では今のところ、電力価格の上昇が避けられないという意見が強い。電気代が値上げに向かえば、「ライフライン」という言葉が表すように日常生活への影響を大きく受ける所得層が出てくるのも必至だ。これに対しては、すでに欧州で行われているような政府による金銭的な補助も十分想定される。
化石燃料による一部の発電施設の維持や新設も現実的には必要だろう。化石燃料への投資を再検討する世界的なファンドもあり、ドイツでは天然ガス発電の新設がすでに認められた。日本で進む容量市場の導入はその制度的な取り組みの一例である。ただし、初回と2回目のオークション結果の差が激しく、これによって化石燃料施設の維持が機能するとは考えにくいし、この制度がそのまま長く続くとは思えない。ドイツなどで導入されている戦略的予備力は見直しされる可能性もあり、実効性のある打開策はまだ見えていない。
原子力回帰など、ここぞとばかりに後ろ向きの議論も聞こえてきているが、「必要なことはわかっている」と言いたい。つまり、長期的に見れば、圧倒的な量の再エネ電源だけがこの問題を解決できる、と私は考える。今起きていることも再エネが足らないことが問題なのであって、うまく需給を合わせる程度のレベルではなく、大きくあふれる再エネの発電量が必要なのである。そこまでいけば、余ったものは、EVを含む蓄電池や電気分解による水素製造、メタネーションなど、現状で電力を必要としている用途が列をなして待っている。


 マガジン
マガジン セミナー・勉強会
セミナー・勉強会 オンライン展示会
オンライン展示会